鈴鹿・四日市・亀山で、歯科・矯正歯科・インプラント・ホワイトニング・各種保険診療のことなら大木歯科医院
 鈴鹿インプラント矯正クリニック
鈴鹿インプラント矯正クリニック
三重県鈴鹿市南長太町鎗添2504-2 受付時間 8:30より 診療時間 9:00〜19:30
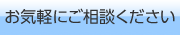
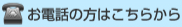 059-395-1000
059-395-1000
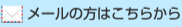 ohkident@mecha.ne.jp
ohkident@mecha.ne.jp
◎食品添加物とは
食品をきれいに見せたり、長持ちさせたりするために添加するものです。
食品衛生法では、「添加物は、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、浸潤その他の方法によって使用する物」と定義されています。
◎食品添加物のメリットとデメリット
メリット
デメリット
過剰摂取については、一日摂取許容量や使用基準が定められ、過剰摂取にならないように配慮されているが、加工食品に偏った食生活が続くと一日摂取許容量を上回る可能性があります。
添加物の使用は、ヒトが一生涯にわたって摂取するものであるため、食品メーカーは添加物の使用を必要最小限にとどめ、消費者に正しく表示する義務があります。
一日摂取許容量とは
ヒトが一生涯、毎日、その添加物を食べ続けても、影響の出ない一日あたりの摂取許容量のことです。
最大無作用量とは
ネズミを使った実験において、どのネズミにも影響の見られなかった投与量
また、28日、90日、1年間におよぶ長期間投与において求められます。
一日摂取許容量=最大無作用量×安全係数(1/100)
ヒトの場合は動物実験で安全な量の、さらに1/100も少ない量に設定されているので安心です!
食品添加物は決して体に悪いわけではなく、私たちの食生活においてなくてはならないものです。何でも取り過ぎには注意して、バランスよく食べることを心がけましょう!!
食中毒と聞くと夏場に多く発生するイメージがあるかもしれませんが、「ノロウイルス」による食中毒は秋から冬にかけて多発します。
食中毒の中でもノロウイルスによる食中毒は年間で最も患者数が多く、集団発生も見られる感染力が非常に高いウイルスです。
ノロウイルスの感染経路は、ほとんどが口から摂取して感染する経口感染で、次のようなパターンがあると考えられています。
①患者のノロウイルスが大量に含まれるふん便や吐ぶつから人の手などを介して二次感染した場合
②ヒトからヒトへ飛沫感染など直接感染する場合
③食品を扱った人が感染しており、その人を介して汚染した食品を食べた場合
④汚染されていた二枚貝を、生あるいは十分に加熱調理しないで食べた場合
⑤ノロウイルスに汚染された井戸水や簡易水道を消毒不十分で摂取した場合
特に、食中毒では③のように食品を取扱う人を介してウイルスに汚染された食品が原因となっている例が、近年増加傾向になっています。
◎ノロウイルス食中毒の予防のポイント
ノロウイルス食中毒を防ぐためには・・・
☆食品を扱う人や調理器具などからの二次汚染を防止すること
☆特に子どもやお年寄りなどの抵抗力の弱い方は、加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱すること
が重要なポイントとなります。
そのためには・・・
◯調理を行う前、食事の前、トイレに行った後、下痢等の患者の汚物処理やオムツ交換等を行った後は必ずしっかり手を洗う。
◯汚染のおそれのある調理台や調理器具は、85℃以上の熱湯での加熱や、次亜塩素酸ナトリウムを用いた殺菌を行う。
(※家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用できます。(使用に当たっては「使用上の注意」を確認しましょう。)
◯調理担当者は健康管理に注意し、下痢などのあるときは調理しない。
◯汚染のおそれのある二枚貝などの食品は、中心温度85℃~90℃で90秒以上の加熱をする。
などの点に気をつけることが大切です。
冬も食中毒に気をつけて、おいしく食事をしましょうね!
遺伝子組み換え食品のとは
生物の細胞から有用な遺伝子を取り出し、別の植物などにその遺伝子を組み込んで新しい性質を持たせることです。
これまでも、品種改良(掛け合わせ)として交配などを行ってきていましたが、交配した中から良いものを選んで、
それをさらに育てなければいけないなど、生産の効率が悪いのが難点でした。
しかし、この遺伝子組換えであれば、必要な遺伝子だけを取り出し、
消費者と生産者が求める性質のものを効率よく作ることができ、
さらに植物から植物にだけでなく、動物から植物へなど種を超えて遺伝子を組み込むことができるようになりました。
この技術により、害虫に強い作物ができたり、除草剤をまいても枯れにくい作物ができたり、
ある特定の成分の含有量が多い作物が作られるようになり、また生産性を上げるための添加物もできました。
日本で安全性が確認され、販売、流通が認められている主な作物
大豆、なたね、ジャガイモ、とうもろこし、わた、てんさい、アルファルファ、パパイヤ
ex:大豆であれば、製油用から大豆油や脂肪大豆ができ、
食品用から豆腐や醤油、納豆、揚げ油などが作られ、他にも飼育用など様々な用途のものが作られています。
複数種の薬と薬の相互作用は多く知られていますが、食べ物においても昔から「食べ合わせ」の問題が知られています。
例えば「うなぎと梅干し」「さばとすもも」「タコと柿」などです。これらの食べ合わせは一過性の消化不良を引き起こす可能性があります。
うなぎやさばは脂肪分が多く、胃の中に入ると胃酸の分泌が抑制され小腸におけるリパーゼの作用を活性化させます。しかし梅干やすももなどの酸性食品を同時に多く食べることで脂肪の消化の妨げになります。
また柿はペクチン質という成分が多く、主成分であるガラクツロン酸(複合多糖類)はヒトの消化酵素では消化できないということと、晩秋以後気温の低下とともに美味しくなるので、酢で締めたタコを冷えた柿と一緒にたくさん食べれば消化不良を起こすことになります。
これらのように注意しなければいけない食べ合わせもありますが、過度な食事をしなければ心配ありません。多すぎず少なすぎず、食材をバランスよく食べることで、健康的に、しっかりと栄養をとりましょう。
「大根のビタミンCをニンジンの酵素(アスコルビナーゼ)が破壊する」
「タンニンの多い渋茶を飲み過ぎると、鉄の腸からの吸収が悪くなる」
「リン酸を摂りすぎると、カルシウムの尿中への排泄が多くなる」
などのように、食べ物に含まれる成分どうしが起こす栄養学的問題もありますが、食べ物と医薬品を同時に摂った場合にも、それぞれの成分が互いに影響しあって栄養素の損失や、薬の効果がかわったりすることがあります。
①薬の吸収遅延
食べ物の栄養素の吸収が優先され、消化活動中は薬の吸収が遅延します。特に軽い食事と重い食事(高タンパク質食、高脂肪食)とでは薬の効果があらわれる速度に違いがあります。
②薬の吸収促進
食べ物と薬の成分どうし相性が良いと、薬の吸収が早まることがあります。
③薬の吸収抑制
食べ物の特殊な成分が薬の成分とくっつくことにより、薬の吸収を抑制します。
④栄養素の吸収が妨げられる
薬の成分が食べ物の成分とくっついて、栄養素の吸収が妨げられることがあります。
これらの作用をもたらす場合には、薬の使用目的にあわせ食事時間と服用時間を調整する必要があります。
☆食品の保存性を高めるもの
◎保存料
微生物による腐敗・変敗を防止することにより、食品の保存性を向上させたり食中毒を予防するた めに開発されました。
◎防カビ剤または防ばい剤
外国産のオレンジ、レモンなどのかんきつ類やバナナは、長時間の輸送や保存中にカビが発生する ことがあります。それを防止するために用いられます。防カビ剤を使用したかんきつ類やバナナを 販売する際には、バラ売りであっても値札や品名札あるいは陳列棚などに、使用した物質名を分か りやすい方法で表示するよう定めています。
◎殺菌料
保存料の微生物に対する作用が静菌的であるのに対して、殺菌料は微生物に対して殺菌的に作用 し、比較的短時間に微生物を死滅させることができます。また、殺菌料は漂白作用もあることか ら、食品に添加されたり、食器類、食品製造機器類などの殺菌目的に使用されています。
◎酸化防止剤
特に油脂類が酸化されると色や風味が悪くなるばかりでなく、酸化によって生じた過酸化物による 消化器障害を引き起こすことがあります。また、褐変や退色、栄養価低下の原因にもなります。
☆食品の嗜好を高めるもの
◎甘味料
甘味料はわたしたちの食欲を満たすためにも、重要な役割をしている食品添加物のひとつです。砂 糖は使用量の増加にともなって、肥満や虫歯などの原因となり、ノンカロリー、低カロリーの甘味 料が使用されるようになりました。
◎着色料
食品が持つ色は、食欲を増進させたり、食生活を豊かにする効果があります。しかし、自然の状態 の色は、日光、酸素などにより変色したり、脱色することがあり、長期にわたってきれいな色を維 持することは難しいです。そこで、加工食品の色を人為的に着色するために着色料が使われていま す。
◎発色剤
発色剤は着色料とは異なり、それ自身に色は着いていませんが、食品中の成分と反応し有色成分と なったり、食品中の色素成分を安定させたりする作用をもつ食品添加物です。
☆食品添加物のマイナスなイメージだけが取り上げられがちですが、食品添加
物にはこのようにさまざまな用途があり、わたしたちの食生活にはかかせません。
食品添加物をたくさん摂ってはダメ!というのではなく、何でも取り過ぎは
よくありません。バランスの良い食事を心がけましょう!!
食品が腐ることを防止するには…
原因→微生物の増殖
食品を低温に保って、微生物の増殖を防ぎましょう!!
◎冷蔵では、低温で増殖する菌や冷たいところを好む菌がだんだんと増殖して食品の品質劣化が起こ
るため、短期間の保存しか出来ません。
◎冷凍では、微生物の増殖はほぼ完全に抑制されるため長期保存ができます。
しかし、菌は完全に死ぬことはないので、取り扱いには注意が必要です。
◎さつまいも、なす、きゅうり、トマト、バナナなどは低温障害を起こして変質するので、室温で保
存することが望ましいです。
冷蔵・・・10℃以下(5℃前後) 食品一般
チルド・・・0℃前後 生鮮魚貝類、食肉など
パーシャルフリージング・・・0〜−3℃ 魚貝類の干物など
冷凍・・・−15℃以下 冷凍食品
他にも、食品が腐ることを防ぐために
などの方法があり、食品添加物も食品を長持ちさせるために重要です。
正しく食品を保存して安全に食事をしましょう!!
「アクリルアミド」という名前を聞いたことはありますか?
実は、身近な食べ物からも生成される物質で、発がん性をもつおそれがあると言われているものなのです!
今回はこのアクリルアミドについてお話ししていきます。
●アクリルアミドって?
アクリルアミドとは、炭水化物を多く含む食品を高温(120℃以上)で加熱調理することにより、食品中のアミノ酸の一種が反応して変化し生成される物質です。
私たちが摂取しているアクリルアミドを食品グループ別でみると、以下のような割合になっています。
高温調理した野菜(炒めたもやし、フライドポテト、炒めたたまねぎ、炒めたれんこん、炒めたキャベツ等)
→56%
飲料(コーヒー、緑茶・ウーロン茶、麦茶等)
→17%
菓子類・糖類(ポテトスナック、小麦系菓子類、米菓類等)
→16%
●アクリルアミドは体に悪いの?
国際がん研究機関( IARC : International Agency for Research on Cancer )による発がん性分類において、「人に対する発がん性の証拠は不十分だが、動物実験における発がん性の証拠は十分にある」ことから、アクリルアミドは2A(人に対しておそらく発がん性がある)に分類されています。
また、食品安全委員会による評価においても、「合理的に達成可能な範囲で、できる限りアクリルアミドの低減に努める必要がある」と結論付けられています。
●どうすればアクリルアミドの摂取量を減らすことができるの?
アクリルアミドの摂取量を控えるために、特定の食品の摂取を控えるなどの偏った食生活を送ると、人体に必要な栄養成分を十分に摂取できなくなるおそれがあります。
同じように、アクリルアミド生成を恐れて食品の加熱をむやみに控えると、食中毒のリスクが高まる可能性があります。
アクリルアミドの摂取量を減らすために大切なのは、十分な果実、野菜を含む様々な食品をバランスよく摂り、揚げ物や脂肪分が多い食品の過度な摂取を控えることです。
バランスの良い食生活を送ることで、アクリルアミドを多く含む食品の摂取量も大きくならないので、食品全体から摂取されるアクリルアミドの量も抑えることになります。
●まとめ
バランスの良い食生活を送るとともに、調理加工条件を工夫することで、アクリルアミドの摂取量を減らすことができるということがわかりました。
また「アクリルアミド」を通して・・・
・様々な食品をバランスよく摂取すること
・調理法のバランスにも気をつけること が大切であるということもわかりましたね。
バランスの良い食生活を送り、健康的な毎日を過ごしましょう!
